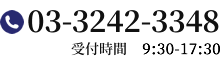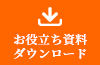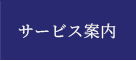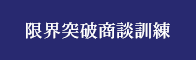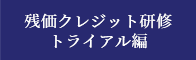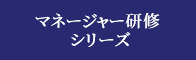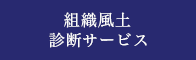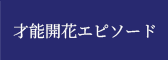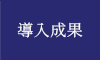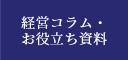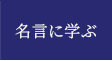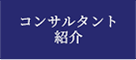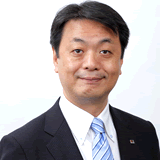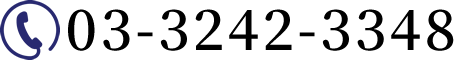指導者は、人、物すべてをあるがままにみとめなくてはならない松下 幸之助
変えられない本質は、あるがままにみとめて、どうすべきかを考えることが大切である
感情的になる人、他責傾向の人、視野が狭く思慮が浅い人は、特に「あるがままにみとめる」ことができません。従って、指導者は、冷静、自責などの姿勢を養い、本質を見抜く洞察力を鍛えることが必要だと感じます。
ある時、部下の育成について相談を受けました。商談や事務処理のミスを指摘し助言すると「分かりました」と返事をするのに、ミスを繰り返す部下がいると言うのです。私は、「彼は分かったつもりだが、理解度が低いと思うので、何が分かって何が分かっていないかを毎回、確認してみてください。」と助言しました。その後、彼が見違えるように成長してくれたと嬉しい報告を頂戴しました。
私も若い頃は、人や組織を相手に「なぜできないんだ」と苛立ちを感じました。しかし、感情的になるのは愚かだと気づき、「どうしたら上手くいくのか」を楽しもうと気持ちを切り替えました。
27歳で課長に就任してから35年の間、一緒に仕事をした部下は200人を超えますが、厳しく叱責したのは3人しかいません。「保身のための嘘をつく。やりもしないでできない言い訳をする。」など不誠実な言動を3回繰り返した部下には、冷静さを保ちながらも厳しく叱責しました。叱責した3人中、2人は1ヵ月もすると姿勢を改めてくれました。残念ながら1人は、幼少期、父の虐待から逃げるために嘘が常習化しており改められませんでした。彼には適性が無いと判断し転職を勧めました。
残る約200人の部下も甘やかしたわけではありません。あるがままに認めて、一人一人のレベルに応じた適度なストレッチをかけて的確な助言をすれば、ほとんどの人は立派に成長してくれました。人材育成で大切なのは、人を見る目を養うことだと考えています。そのため、最近では、基礎能力を8項目(規律正しさ、整理整頓、マナー、素直さ、誠実さ、冷静さ、相互理解力、向上心)で評価し、一人一人に不足する能力を向上するよう求め、習慣が改まるまで指導を続けています。
 株式会社アビリティブルームコンサルティング
株式会社アビリティブルームコンサルティング