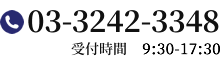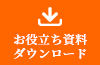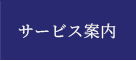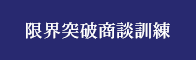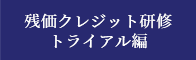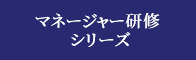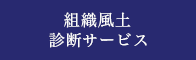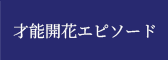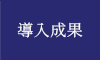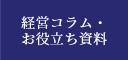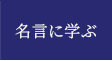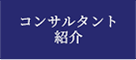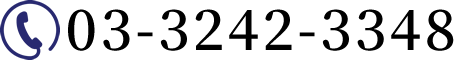見える化の基本は、相手の意思にかかわらず、さまざまな事実や問題が「目に飛びこんでくる状態」をつくり出すことである。「見る」でなく「見える」という言葉を使っているのには、そんな意味合いが含まれている遠藤 功
ローランドベルガー社の会長を務める遠藤功氏は、「見える化」の元祖であるトヨタ自動車を研究し、数多くの書籍を出版しています。中でも「見える化」は名著です。
様々なディーラー拠点で、改革推進を支援しますが、支援開始の際、現状をヒアリングします。代替、点・車検、保険、割賦、カーケアなど増大を目指すものの停滞することが多いようです。その問題点は、以下のとおりです。
- 改革テーマについて、目標がプロセスに分解されていない
- プロセス目標を設定しているがスタッフ個別に割り振られていない
- プロセス目標が個別に設定されているが「見える化」されていない
特に、この③で留まるケースが非常に多いです。冒頭の名言には続きがあります。
「『人間は問題が目に飛び込んでくれば行動を起こす』という動物的本能に訴えかかけるのが『見える化』のポイントなのだ。だからこそトヨタのアンドンも、現場管理者が担当職場のどこからでも『目に飛び込んでくる』ような大きな掲示板を天井から吊り下げているのである」 中略
「多くの場合が、IT(情報技術)に過度に依存した仕組みになっていて、自然に目に飛び込んでくる『見える化』でなく、人間の意思を前提にした『見る化』で終わってしまっている」
どこの職場もIT化が進み、「『見える化』しています」と胸を張る店長、リーダーが沢山いますが、実は「見る化」で終わり、低迷するスタッフに聞いても、改革テーマに掲げた重要な実績データを見ていない、自分が未達であることを知らないということが非常に多いのです。
特に、成長、発展を目指し、組織を挙げて推進する改革では、問題が自然と飛び込んでくる『見える化』を上手に駆使したいです。
引用:遠藤功著「見える化」 東洋経済 2005年
 株式会社アビリティブルームコンサルティング
株式会社アビリティブルームコンサルティング